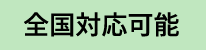
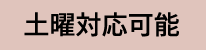

Consumer ADR
東京都千代田区富士見2-4-6 宝5号館2F
認証番号:第10号
認証年月日: 平成 20年 3月19日
氏名又は名称
公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会(東京) JCN6013205001715
民間紛争解決手続の業務に用いる名称
Consumer ADR
住所
東京都千代田区富士見二丁目4番6号
代表者氏名
河上 正二
電話番号
(03)6434−1125
ホームページアドレス
認証紛争解決手続きの業務を行う事務所
名称
Consumer ADR
住所
東京都千代田区富士見2-4-6 宝5号館2F
電話番号
(03)6434-1125
業務を行う日及び時間
[消費者相談] 日曜日の午前11時から午後4時まで(年末年始を除く) [裁定手続] 月曜日・水曜日・木曜日の午前10時から午後4時まで(祝祭日および年末年始を除く)
アピールポイント・解決事例等
①ConsumerADRは、NACSの消費者相談を受けることを前提としています。この消費者相談は、土曜日・日曜日に実施されているので、平日仕事等で時間の取れない方も相談ができるようになっています。また、相談の段階で、事案の内容を詳しく聞き取り事実関係の整理ができるため裁定手続に移行してから手続をスムーズに行えます。
[消費者相談]
土曜日(年末年始を除く)10時~12時、13時~16時 TEL:06-4790-8110
日曜日(年末年始を除く)11時~16時 TEL:03-6450-6631
②手続実施者の弁護士は、消費者問題に精通し実績のある弁護士が担当します。また、他の手続実施者は、消費生活アドバイザー、消費生活コンサルタント、消費生活相談員のいずれかの資格を有し、かつ消費者相談業務に関し3年以上の実務経験のある者が務めます。
【アピールポイント】
消費者相談員が丁寧に聞き取りをします。訪問販売や通信販売など特定商取引のトラブルはあきらめずにまずは気軽に週末電話相談にご相談ください。
1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)
○特定商取引に関する法律に規定する特定商取引(例:訪問販売、電話勧誘販売等の取引)に関する紛争
2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)
○Consumer ADRの運営を担当する特別委員会が、案件ごとに候補者名簿に記載されている者のうちから、担当手続実施者3名(うち1名は弁護士)を選任する。
3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)
○消費者問題専門家(消費生活アドバイザー又は消費生活コンサルタントの資格を有し、各地の消費生活センター等において相談業務の経験を有する者等)
○弁護士
4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)
○普通郵便、ファクシミリ、電子メール、電話、口頭による方法その他適宜の方法により行う。但し、次の通知は、配達証明郵便で行う。
(1)申立ての受理又は不受理の通知
(2)相手方(事業者)に対する確認の通知
(3)相手方(事業者)が裁定手続に応じず手続が終了した場合の通知
(4)和解書の送付
(5)申立ての取下げ又は終了の申出により手続が終了した場合の当事者への通知
(6)担当手続実施者が和解が成立する見込みがないものとして手続が終了した場合の当事者への通知
(7)その他の事由により手続が終了した場合の当事者への通知
5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)
↓PDFファイル参照
【PDF】【PDF】
6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)
【申立人(消費者)】
(1)消費者であって、次のいずれかの者であること
・特定商取引の契約者
・特定商取引の契約の成立若しくは効力を争う者
・その他これに準ずる者としてConsumer ADR特別委員会委員長が認めた者
(2)当協会の消費者相談を受けていること
(3)裁定手続申立書に次の資料を添付して提出すること
・紛争に係る契約書又はその写し
・代理人を選任したときは、その権限を証する書面
・その他参考となる資料
(4)裁定手続申立書の提出と同時に、申立費用(5,000円)を納付すること
【相手方(事業者)】
○裁定手続に応じる旨を記載した裁定手続依頼書を当協会に提出すること(ファクシミリ、電子メール又は電話による裁定手続の実施の依頼も可)。
7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)
○相手方(事業者)に申立てに応じて裁定手続の実施を依頼するか否かを確認するため、その意思について照会する書面を送付する。
8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)
○資料を提出した当事者から請求があったときは、写しを作成し原本を返還する。
※返還請求のなかった資料については、裁定手続が終了した日から10年間保管する。
9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)
○裁定手続は、非公開とする。
○当協会の役員及び職員、手続実施者候補者、Consumer ADR特別委員会委員、苦情処理委員会委員、事務担当職員には、その職を退いた後も含めて守秘義務が課せられている。
○提出された書類及び資料は、秘密を保持するため施錠のできる保管庫等の保管設備に保管し、電磁的記録についてはアクセス制御等の措置を講じる。
○保存期間を経過した文書は、Consumer ADR特別委員会委員長において、文書の記載事項が判読できないように裁断し、電磁的記録には無効情報を上書きする等の方法により記録された情報が復元できない措置を講じ、廃棄する。
10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)
○当協会に所定の書面を提出して行う。
○手続期日においては担当手続実施者(裁定委員会)に口頭で終了の旨を告げることで可
11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)
○申立人は、申立費用5,000円を申立てと同時に現金で当協会に支払う。
○当協会が指定する金融機関の口座へあらかじめ振込む。
12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)
○裁定手続に関して苦情のある者は、苦情申出書を当協会に提出
○ConsumerADR特別委員会委員長は、苦情処理委員会を招集し、苦情の事情の調査及び苦情処理の方法の審議を行わせる。
○ConsumerADR特別委員会で、審議の結果を基に苦情処理の方法を決定し、苦情を申し出た者に書面又は口頭により通知する。
13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)
○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。
※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。
○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。
ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
| 受付事件内訳 | ||
|---|---|---|
| 新受 | 既済 | 未済 |
| 0 | 0 | 0 |
| 年度・期間 | |
|---|---|
| 2023 | 2023年04月01日〜2024年03月31日 |
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
| 価格の別 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60万円以下 | 60万円超~ 140万円以下 | 140万円超~ 300万円以下 | 300万円超~ 1000万円以下 | 1000万円超~ 1億円以下 | 1億円超 | 算定不能又は不明 | 計 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当事者の別 | 代理人(法定代理人を除く。)の別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 双方が法人 | 一方が法人 | 双方が個人 | 計 | 双方代理人 | 一方代理人 | 双方代理人なし | 計 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 終了事由の別 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成立 | 見込みなし | 双方の離脱 | 一方の離脱 | その他 | 小計 | 不応諾 | 計 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
| 手続実施者の別 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | |||||||||
| 0 | |||||||||
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
| 所要時間 | 件数 |
|---|---|
| 1月未満 | 0 |
| 1月以上-3月未満 | 0 |
| 3月以上-6月未満 | 0 |
| 6月以上-1年未満 | 0 |
| 1年以上-2年未満 | 0 |
| 2年以上 | 0 |
| 計 | 0 |
| 所要回数 | 件数 |
|---|---|
| 1回 | 0 |
| 2回 | 0 |
| 3回 | 0 |
| 4回 | 0 |
| 5-10回 | 0 |
| 11回以上 | 0 |
| 計 | 0 |
| 手続実施方法 | 件数 | |
|---|---|---|
| 面談のみ | 0 | |
| 面 談 以 外 | 電話 | 0 |
| 電子メール | 0 | |
| ファクシミリ | 0 | |
| 文書の送付 | 0 | |
| その他 | 0 | |
| 小計 | 0 | |
